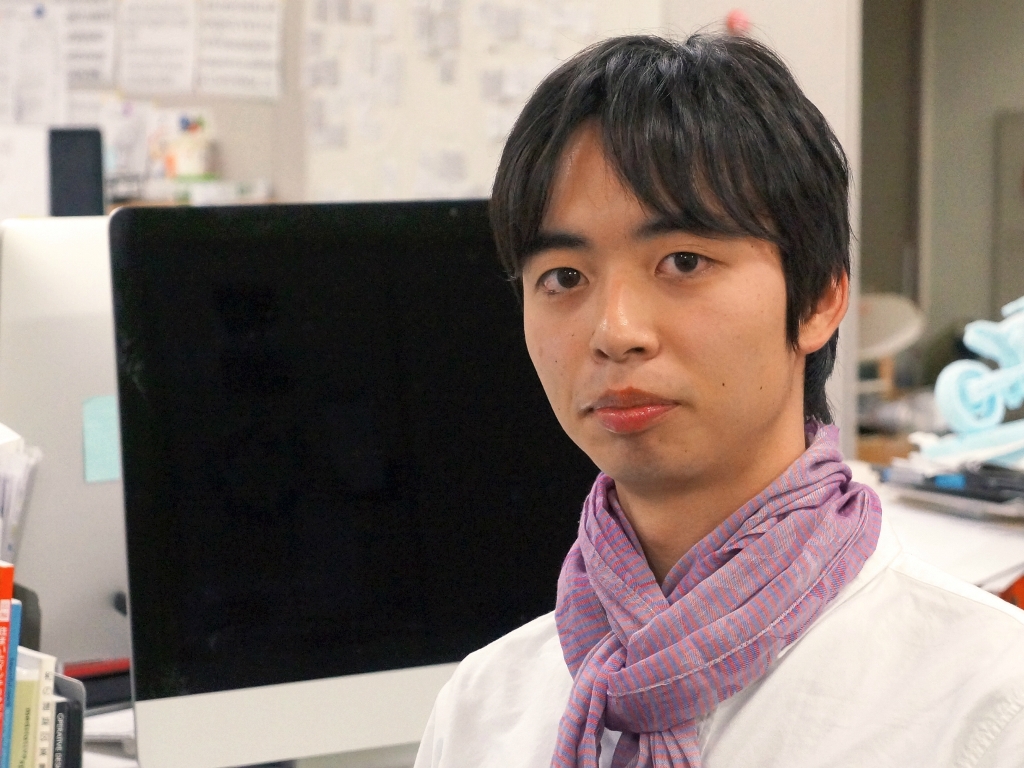はじめに:ユーザーの知見=外部からの発想
ヒューマンセンタードデザインやデザイン思考は、ビジネスを行う企業にとって「外部」であるユーザーを起点とした考え方です。ただ、ユーザーからの知見は「今あるもの」を磨き上げること=演繹的にすでにある解を見つけ出すことは得意ですが、「今あるもの」から大きくジャンプする真のイノベーションを起こすことができるとは限りません。同質的なチームの罠
特に、同質的なチームでワークショップ等を繰り返していると、チームにおいて「経路依存性=ロックイン効果」の罠にかかってしまい、イノベーションの機械に対して認識が狭くなってしまいます。 一般的には5〜7年以上にわたって同質的な集団に所属していると、組織の外にある異なる価値観や知識を吸収しなくなる傾向がメンバーに見られるようになります。(=Not Invented Hereシンドローム(NIH症候群))ダイバーシティの重要性
そこで、必要なのがチームメンバーの多様性(ダイバーシティ)の確保です。ここでのダイバーシティは専門領域の違いの事です。メンバーの多様性の低い集団から得られる成果の金銭的な価値=イノベーションは中程度に留まります。ですが、メンバーの多様性が高くなればなるほど、価値の低い成果も増えるものの、ブレイクスルーとなる価値の高い成果も得られるのです。デザイン・ディスコースの可能性
では、多様なメンバーから生み出される成果が価値の低いもの(失敗)ではなく価値の高いもの(イノベーション)になるには何が必要なのでしょうか。たくさんのアイデアを試してみることでしょうか。たくさんのアイデアを考えることは先述の演繹的にモノの改善行う場合には有効ですが、「新しい意味」を見出し「意味のイノベーション」を導くときには役に立ちません。その答えこそが、演題にもなっている「デザイン・ディスコース」なのです。「デザイン・ディスコース」とは「あるデザインが、社会的な文脈の中で、何を意味し、また、なぜそれが必要なのかを、様々なステークホルダーとの対話を通して分析すること」です。
「新しい意味」と「意味のイノベーション」:テクノロジーによる問題解決が「どうやって?」を追求するのに対し、「新しい意味」は「なぜ?」を追求します。その結果生まれる「意味のイノベーション」は使い方、シンボル、ユーザーの感情の3つに変化を起こします。これこそが「Design Driven Innovation(デザイン駆動型イノベーション)」と言えるのです。
デザイン・ディスコース、その前に〜批判の精神〜
デザイン・ディスコースを行う前に必要なことがあります。それは、ユーザー=外部ではなく、個人や自社=内部から従来のモノの前提に疑問を投げかけていく姿勢=「批判の精神」です。「批判の精神」持って、1.個人、2.ペア、3.小さなサークルと少しずつ輪を大きくしながら、建設的に異なる意見を浮かび上がらせていきます。結果として、対照的な点から、大胆で新しいコンセプトに至るのです。議論の過程では「共通の敵」を想定し、「メタファー」を通してコンセプトとビジョンを明確化することが有効です。デザイン・ディスコースと解釈者
そして、第4段階として解釈者による批判=デザイン・ディスコースを行います。まとめられたビジョンが解釈者による批判に晒されることで、的確な疑問の声から新たなモノの意味が確固たるものになります。多様なモノサシ=認知を持った解釈者は、既存のモノサシ=認知から計られる既存の意味を取り払ってくれる存在なのです。80~90年代の日本企業には確固たる意志を持った解釈者がどの企業の中にいたという意見が出ました。そして、その後普及したHCDにおけるモノサシはユーザーであったと言えます。
おわりに:イノベーション、ビジネス、デザイン、アート…
このように考えると、(いわゆる現代)アーティストは広い意味で解釈者にと言えるのではないでしょうか。単に解釈するだけでなく、物事の捉え方を根元から見直し、それを作品を通して発信しているのです。例えば、マルセル・デュシャンやジョン・ケージは作品を通して芸術・音楽とは何かという根元に「問題のありか」を発見し、既存の認知に問いを投げかけたのです。このようなアートの力を利用し、企業が新しく柔軟な考え方を得る試みを「Artistic Intervention(アートによる介入)」と言い、ヨーロッパを中心に行われています。Artistic Interventionによって、企業は「考えるべき問題のありか」を探すことで、他社が簡単に真似できない意味のイノベーションを起こせる可能性があります。
ただ、ビジネスとアートはまだ水と油の関係のため、翻訳者・ファシリテーターとして、デザイナーの能力が活かせる可能性があります。
ビジネスパーソンとアーティストをデザイナーがファシリテーターとして結びつける場合、アーティストに求められているのはクリエイティブ能力、デザイナー必要なのはコミュニケーション能力となるます。ただ、デザイナーはクリエイティブ能力とコミュニケーション能力の両方を身につけておくことがふさわしく、以前はそうであった、という意見も出ました。
レポート作成者による感想
今回のSKELセミナーでは、ダイバーシティの重要性を理解するとともに、内部から新たな意味を探ること、それを後押しする解釈者の意義を皆で共有できたと思います。また解釈者の中の解釈者であるアーティストとビジネスの可能性を知ることができました。「Artistic Intervention」は、所謂スペキュラティブ・デザイン(問題提起型デザイン)に近い事柄かと思います。私自身は「問題解決としてのデザイン」を学んできたのですが、今回の講義は、それとは異なる新しいデザイナーの役割を考える、また最後に先生がおっしゃった「デザイン固有の領土」について考えるきっかけとなりました。次回以降、また皆様とディスカッションを行っていければと思います。



 Archives
Archives